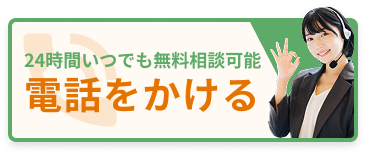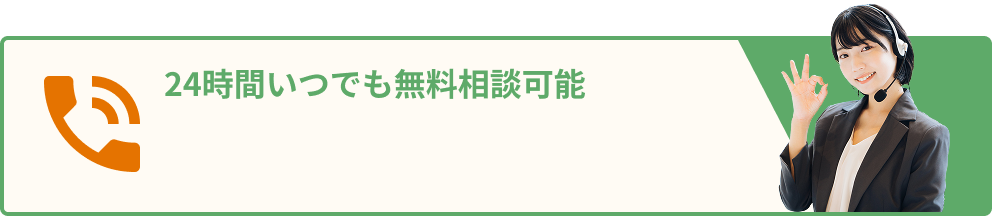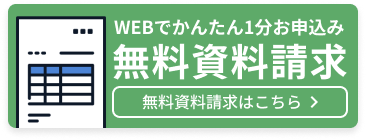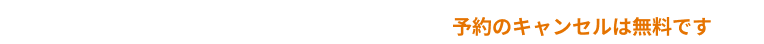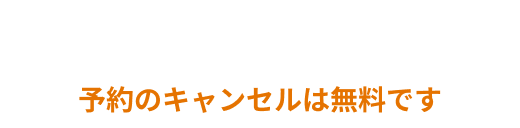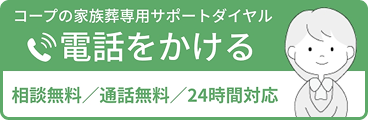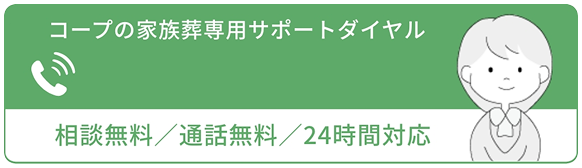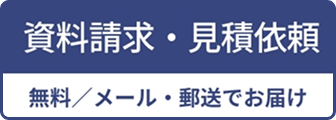浄土真宗の葬儀の流れ|独自の作法やマナーを解説
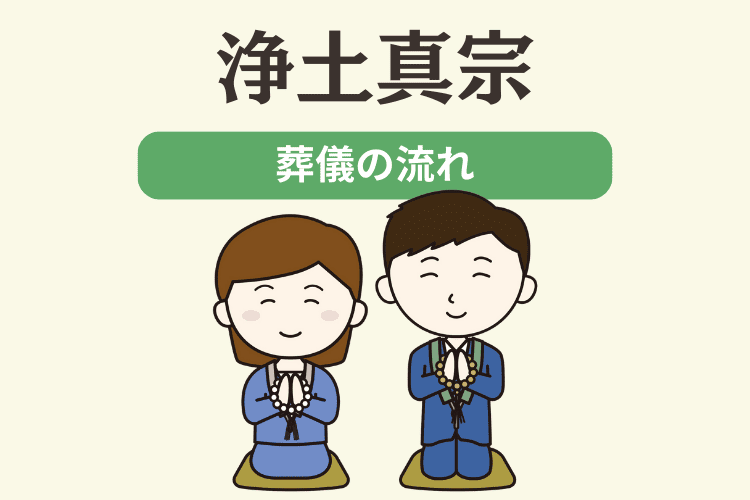
「浄土真宗の葬儀ってどのように進む?」
「浄土真宗独自のマナーや作法を知りたい」
「浄土真宗の葬儀に参列するにあたって失礼がないようにしたい」
浄土真宗は、他の仏教宗派と異なる点が多々あります。
また、浄土真宗のなかでも10の派に分かれており、それぞれで式次第が若干異なる点が特徴です。
初めて浄土真宗での喪主を務める、また参列する方にとっては戸惑う点も多いでしょう。
本記事では、浄土真宗のなかでも門徒(信者)の人数が多い「本願寺派」「大谷派」の葬儀の流れを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
|
<この記事でわかること>
・浄土真宗について ・浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ ・真宗大谷派の葬儀の流れ ・浄土真宗にのみない慣習 ・浄土真宗独自の作法・マナー |
浄土真宗とは

浄土真宗とは、鎌倉時代初期に「親鸞(しんらん)」によって作られた仏教宗派です。
本尊である阿弥陀如来を信じ「南無阿弥陀仏」を唱えれば誰でも極楽浄土へ生まれ変われると説いています。
他の宗派と異なり、逝去後に仏様の弟子となり修行をする必要がありません。亡くなったらすぐに仏となれる「即身成仏(往生即成仏)」の教えが特徴です。
そのため、浄土真宗には他の宗派に見られない独特の流れ・作法・マナーが存在します。
浄土真宗における葬儀の意味・目的

浄土真宗の葬儀は、死者を供養する目的で行われません。
亡くなったらすぐ阿弥陀如来によって極楽へ迎えると信じられているため、供養する必要がないのです。
「では、なぜ葬儀を行うのか」と思うかもしれません。浄土真宗の葬儀は「聞法(もんぼう)の場」としての意味があります。
聞法とは、仏様の教えを聞き学ぶ場を指します。
浄土真宗では、逝去に際して家族・親族・友人が集まり、故人を忍びつつも阿弥陀如来の教えを聞いたり、感謝を伝えたりといった場として葬儀を執り行うのです。
そのため、礼拝するのは故人ではなく阿弥陀如来、というのが浄土真宗の葬儀の特徴です。
浄土真宗の葬儀の流れ

浄土真宗には、10の派が存在します。なかでも大多数の門徒(信者)を抱えているのが本願寺派と大谷派です。
本願寺派・大谷派いずれの場合も、基本的には以下の流れで葬儀が進みます。
| 浄土真宗の基本的な葬儀の流れ | |
|---|---|
| 1.逝去 | ・故人を北枕に寝かせる
・清拭・湯灌・必要に応じてエンバーミングを施す ・顔に白布をかけ、白服を掛ける |
| 2.臨終勤行 | 阿弥陀如来に対して読経を行う |
| 3.お通夜 | 一晩中線香を絶やさないようにする必要はない |
| 4.葬儀 | 葬儀後に出棺式を行う |
| 5.火葬 | 火葬・収骨を行う |
また、地域によっては「5.」の順番が前後し「1.逝去→2.枕経→5.出棺・火葬→3.お通夜→4.葬儀」と進む場合もあります。
初めての葬儀で順番がわからない方は、葬儀社か菩提寺へ確認しましょう。
以降では、本願寺派・大谷派に分けて葬儀の流れを解説します。
出典:文化庁「宗教年鑑・令和5年度版」
浄土真宗本願寺派|逝去〜葬儀終了までの流れ

浄土真宗本願寺派の逝去〜葬儀終了までの流れを、以下4つの場面に分けて解説します。
- 本願寺派の逝去当日
- 本願寺派のお通夜
- 本願寺派の葬儀
- 本願寺派の火葬
ひとつずつ見ていきましょう。
本願寺派の逝去当日
逝去当日は、ご遺体を安置したあとに「臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)」をします。
僧侶が読経し、本尊(阿弥陀如来)に対してお勤めをする儀式です。他の仏教宗派における「枕経」に該当します。
他の仏教宗派では故人を供養するために行いますが、浄土真宗では本尊に対して行うのが特徴です。
本来は本人(故人)が生きているうちに行う儀式でしたが、実際は亡くなられてからするのが一般的です。
また、生前に法名(戒名)を授けられていない場合は、臨終勤行でもらうケースが多く見られます。
本願寺派のお通夜
本願寺派のお通夜は、以下の流れで進みます。
| <浄土真宗本願寺派のお通夜の流れ>
1.遺族・参列者入場 遺族や参列者が会場に入場します。
2.導師(僧侶)入場 導師(僧侶)が会場へ入場します。
3.勤行 「阿弥陀経」を読経して勤行を行います。 ご遺体ではなく本尊に向かって勤行をします。 浄土真宗では逝去後すぐに極楽浄土へ行けるとされているため、故人に対する供養の必要がないためです。
4.導師(僧侶)による法話 導師(僧侶)によって浄土真宗の教えを説く「法話」を行います。
5.導師(僧侶)退場 導師(僧侶)が会場から退場します。 ※地域によって流れが異なる場合があります。 |
葬儀後には通夜振る舞いをし、翌日の葬儀の打ち合わせや準備をします。
本願寺派の葬儀
浄土真宗本願寺派の葬儀は、自宅での「出棺勤行」と、葬儀会場での「葬儀勤行」に分けて行うのが本来の形です。
しかし、近年は自宅での葬儀が減少しているため、斎場でとりまとめるのが一般的となっています。
本項で解説するのは、斎場でとりまとめて行う形式の流れです。
| <浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ>
1. 遺族・参列者入場 遺族や参列者が葬儀会場に入場します。
2.導師(僧侶)入場 僧侶が葬儀会場に入場します。
3.開式の辞
4.帰三宝偈(きさんぼうげ) 本来は葬儀場への出棺に先立って行われたものでした。 近年は葬儀場で行われます。 「帰三宝偈(きさんぽうげ)」というお経を唱えます。 仏への帰依を表すお経です。
5.帰敬式(ききょうしき) おかみそり(剃髪の儀)をして法名を授与します。 生前に受けている場合は省略される儀式です。 実際に髪はそらず、動作だけに留めるのが近年の傾向です。
6.路念仏(ろじねんぶつ) 元は野辺送りの際に唱えられていたお経です。 通夜会場と葬儀場が別の場合は移動中に唱えられるケースもあります。 独特の節回しが特徴です。
7.三奉請(さんぶしょう) 法要を始めるにあたって、阿弥陀如来・釈迦如来・十方如来などの諸仏を招くために唱えます。
8.導師(僧侶)焼香 僧侶が焼香を行います
9.表白(びゃくびょう) 葬儀の趣旨を簡単に説明する文を読みます。
10.正信偈(しょうしんげ) 親鸞の「教行信証」の一部を読経します。 正式名称は「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」です。
11.焼香 遺族→親族→一般参列者の順に焼香をします。
12.念仏 「南無阿弥陀仏」を唱えます。
13.和讃 仏様を送る儀式です。
14.回向(えこう) 葬儀や法要の終わりに唱えられるお経です。 念仏を唱えることで得られた功徳を全ての人に回し向ける意味があります。 浄土真宗においては、仏様から人々に及ぼされた巧徳を喜ぶための儀式です。
15.導師(僧侶)の退場 僧侶が葬儀場から退場します。
16.閉式
17.喪主の挨拶 喪主から参列者へ挨拶します。
18.出棺 霊柩車でご遺体を火葬場へ運びます。 ※地域によって流れが異なる場合があります。 |
弔辞・弔電の紹介は、「10.正信偈」の前、もしくは「15.導師(僧侶)の退場」のあとに行われます。所要時間は40分〜1時間前後です。
本願寺派の火葬
火葬場に到着したあとは、以下の流れで進みます。
| <本願寺派の火葬の流れ>
1.火屋勤行(ひやごんぎょう) 火葬の前に「重誓偈(じゅうせいげ)」というお経を唱えます。
2.火葬 ご遺体を火葬します。
3.還骨勤行 阿弥陀仏教の読経・念仏・和讃をして祭壇へ骨壷を戻します。 |
火葬後の遺骨は浄土真宗の本山に分骨する場合があります。分骨する際は、分骨用の骨壷を前もって用意しておきましょう。
真宗大谷派|逝去〜葬儀終了までの流れ

本項では、大谷派の逝去〜葬儀終了までの流れを、以下4つの場面に分けて解説します。
- 大谷派の逝去当日
- 大谷派のお通夜
- 大谷派の葬儀
- 大谷派の火葬
本願寺派と大枠は同じですが、細かな点が異なります。
ひとつずつ見ていきましょう。
大谷派の逝去当日
逝去からお通夜までの流れは本願寺派と変わりありません。ご遺体を安置したあとに臨終勤行を行います。
故人は極楽浄土に行って仏様になるとの教えがあるため、守刀や一膳添えもしません。
大谷派のお通夜
大谷派のお通夜の流れは以下のとおりです。
| <大谷派のお通夜の流れ>
1.遺族・参列者入場 遺族や参列者が葬儀場に入場します。
2.導師(僧侶)入場 僧侶が葬儀式場に入場します。
3.勤行 「正信偈(しんしょうげ)」を読経し、勤行を行います。 本願寺派同様、故人ではなく阿弥陀様に向かって勤行するのが特徴です。
4.導師(僧侶)による法話 浄土真宗の教えを説く「法話」が行われます。
5.導師(僧侶)退場 僧侶が会場から退場します。 |
お通夜後の流れは本願寺派と同じく「通夜振る舞い→翌日の葬儀の準備」と進みます。
大谷派の葬儀
大谷派の特徴は、葬儀が「葬儀式第一」と「葬儀式第二」の2部構成である点です。
本来は、葬儀式第一を自宅で、葬儀式第二を葬儀場で行います。
しかし、近年は自宅で葬儀を執り行う方が減った影響で、式次第を編成して葬儀場にて完結させるケースがほとんどです。
本項では、近年の一般的な流れを解説します。
| <大谷派の葬儀の流れ>
1.遺族・参列者入場 遺族や参列者が葬儀場へ入場します。
2.導師(僧侶)入場 僧侶が葬儀場へ入場します。
3.開式
4.総礼(そうらい) 全員で合掌し、念仏を唱えます。
5.伽陀(かだ) 仏様に来場してもらえるようお願いするものです。 葬儀や大規模な法要の開始時に唱えられます。
6.勧衆偈(かんしゅうげ) 本来は自宅にて行う葬儀式第一で唱えられるものです。 阿弥陀様を信じることを勧める言葉とされています。
7.短念仏十遍 「南無阿弥陀仏」を10回唱えます。
8.回向(えこう) 念仏を唱えることで得られた功徳を全ての人に回し向ける意味があります。
9.総礼(そうらい) 全員で合掌し、念仏を唱えます。
10. 三匝鈴(さんそうりん・さそうれい) 鈴を鳴らします
11.路念仏(じねんぶつ) 本来は野辺送りの際に唱えられていたお経です。 独特な節回しで唱えられます。 お通夜と葬儀の会場が別の場合は、移動中に唱えるケースもあります。
12.表白 お迎えした仏様に法要をする旨を伝えます。
13.三匝鈴(さんそうりん、さそうれい) 鈴を鳴らします。
14.弔辞
15.正信偈(しょうしんげ) 親鸞の「教行信証」の一部を読経します。 正式名称は「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」です。
16.焼香 遺族→親族→参列者の順に焼香をします。
17.短念仏十遍(たんねんぶつじゅっぺん) 「南無阿弥陀仏」を10回唱えます。
18.和讃(わさん) 仏様の徳を讃える歌を唱えます。
19.回向(えこう) 念仏を唱えることで得られた功徳を全ての人に回し向ける意味があります。 浄土真宗においては、仏様から人々に及ぼされた巧徳を喜ぶための儀式です。
20.総礼 全員で合掌し、念仏を唱えます。
21.導師(僧侶)退場 僧侶が葬儀会場から退場します。
22.閉式
23.喪主の挨拶 喪主から参列者へ挨拶をします。
24.出棺 霊柩車でご遺体を火葬場へと移動します。
※地域によって流れが異なる場合があります。 |
大谷派の火葬
火葬場に到着してからの流れは以下のとおりです。
| <大谷派の火葬の流れ>
1.火屋勤行(ひやごんぎょう) 火葬の前に「重誓偈(じゅうせいげ)」というお経を唱えます。
2.火葬 ご遺体を火葬します。
3.還骨勤行 阿弥陀仏教の読経・念仏・和讃をして祭壇へ骨壷を戻します。 |
流れは本願寺派と大きく変わりありません。
大谷派も本山に分骨する習わしがあるため、希望する方は前もって分骨用の骨壷を用意しておきましょう。
浄土真宗の葬儀費用の相場

浄土真宗の一般的な相場は以下のとおりです。
| 浄土真宗の葬儀の一般的な相場(お布施は含まない) | |
|---|---|
| 一般葬 | 100〜120万円 |
| 家族葬 | 80〜100万円 |
| 一日葬 | 30〜60万円 |
葬儀の規模や内容によっては多少前後します。
また、お布施の相場は10〜30万円です。仏式葬儀の全国平均が20〜50万円、北海道の平均が30万円(※)のため、相場は比較的安価といえます。
相場より安い理由は、浄土真宗では戒名料が発生しないためです。
戒名の代わりに「法名」を授かりますが、法名料は戒名料に比べて相場が安く、一般的に0円~30,000円程度です。
他の宗派と比較して戒名(法名)にかかるお布施が少ないため、総額が低くなっています。
(※)自社調べ
【関連記事】葬儀費用の平均は?葬儀費用の内訳や料金を抑える方法を解説
他の宗派にあって浄土真宗にないもの

浄土真宗では、他の宗派では一般的な以下の慣習が存在しません。
- 末期の水
- 枕飾り(枕団子・枕飯・水は不要)
- 死装束
- 引導
- 授戒
- 戒名・位牌
- お清めの塩
浄土真宗で上記の事柄が行われない理由を解説します。
末期の水
浄土真宗では、死者の口を湿らせる「末期の水」を行いません。
末期の水は、極楽浄土への旅路で喉が渇かないように行う儀式です。
亡くなったらすぐに極楽浄土へ向かえるとされる浄土真宗においては不要とされています。
しかし、日本の葬儀慣習として末期の水を行う場合もあります。
枕飾り
故人の枕元に設置する枕飾りですが、浄土真宗では枕団子、枕飯、水は不要とされています。
枕団子、枕飯、水は、故人の供養を目的として設置するものですが、亡くなったら極楽浄土へ辿り着ける浄土真宗においては、供養の必要がないため設置しません。
死装束
死後の旅に出る必要がない浄土真宗では、旅装束としての「死装束」も不要です。
仏衣として死装束をお着せしますが、笠・杖・脚絆などは着用せず、守り刀も持たせません。
地域によっては、故人が気に入っていた着物や洋服などを着せるとろこもあるようです。
また、ご遺族が用意された場合は、門徒式章(門徒肩衣または半袈裟)を肩にかけます。
引導
浄土真宗に「引導」はありません。引導とは、亡くなった方が迷わず極楽浄土へ行けるよう導くための儀式です。
他の宗派では僧侶がお経を唱えて極楽浄土へ辿り着けるよう祈りますが、浄土真宗では阿弥陀様の力によってのみ辿り着けると考えられています。
そのため、他の宗派で行われている「引導」が浄土真宗には存在しないのです。
授戒
仏門に入る者に仏弟子としての戒を授ける「授戒」ですが、浄土真宗では行いません。
浄土真宗には死後に仏門へ入るという考え方がないためです。
戒名
浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」を授かります。
戒名とは、仏弟子となった証として授かる名前です。仏教の戒律を守る意味を込めて「戒名」と呼ばれています。
一方、浄土真宗では戒律がないため「戒名」ではなく「法名」が授けられます。
法名には、必ず文字の頭に「釈」の字を入れるのが特徴です。
生前に「帰敬式」の儀式を持って授けてもらうのが本来の流れですが、逝去後に授かる方も多くいらっしゃいます。
位牌
浄土真宗では位牌を用意しません。亡くなったらすぐに成仏するとされているため、故人の魂を供養する必要がないのです。
葬儀の際に一時的な措置として白木位牌を用意するケースはありますが、四十九日後に本位牌へ代えることはしません。
お清めの塩
浄土真宗では、葬儀後に配られるお清めの塩がありません。
そもそもお清めの塩は、家に穢れを持ち込まないために行う神道の慣習です
日本では神道と仏教が共存しているため、お清めの塩は神道の慣習が仏教と混ざり合い始められたとされています。
浄土真宗では、死者はすぐ仏様になる教えと、そもそも穢れという概念がない点から、お清めの塩は使用しません。
浄土真宗の作法・マナー

浄土真宗では、以下の7つにおいて、他の宗派には見られない独自のマナーが存在します。
- お念仏
- 服装
- 数珠(念珠)
- 焼香
- 香典
- 言葉遣い
- 線香
ひとつずつ解説します。
お念仏
浄土真宗では「浄土三部経」という経典にある「南無阿弥陀仏」を唱えます。
なお、本願寺派は「なもあみだぶつ」、大谷派は「なむあみだぶつ」と読み方が異なるため、参列する際は間違えないよう注意しましょう。
服装
服装は他の宗派と同じく喪服を着用します。
ただし、門徒(浄土真宗の信者)は「門徒式章」または「門徒肩衣」を掛けるのがマナーです。和装・洋装問わず、持っている場合は必ず肩にかけましょう。
なお、本願寺派は「門徒式章」、大谷派は「門徒肩衣」と呼びます。総称のように「半袈裟」と言う人もいますが、いずれも間違いではありません。
【関連記事】初めての葬儀に備える服装のマナー|性別・年齢別で注意点を解説
数珠(念珠)
同じ浄土真宗でも、本願寺派と大谷派では合掌時の持ち方が異なるため、前もって把握しておくと安心です。
| <本願寺派の念珠の持ち方>
・数珠を二輪にする(略式数珠の場合は一輪のまま) ・数珠を左手に掛ける ・房を下に垂らす ・右手を通して合掌 |
| <大谷派の念珠の持ち方>
・数珠を二輪にする(略式数珠の場合は一輪のまま) ・両手を輪に通す ・二輪の数珠は房を左手の甲に垂らす ・略式数珠は房を下に垂らす ・合掌 |
【関連記事】数珠の持ち方や合掌時の掛け方は?葬儀における数珠のマナーを解説
焼香
本願寺派と大谷派では焼香の作法に違いがあります。
| <本願寺派>
1.ご本尊の前で一礼 2.お香を右手親指・人差し指・中指の3の指でつまむ 3.額には押し頂かず1回だけ香炉にくべる |
| <大谷派>/
1.ご本尊の前で一礼 2.お香を右手親指・人差し指・中指の3の指でつまむ 3.額には押し頂かず、2回香炉にくべる |
覚えるのが難しい場合は、自分の宗派の作法でしても問題はありません。
ただし、喪主・遺族の立場の方は、浄土真宗の作法にならって焼香をしましょう。
香典
香典の書き方には、浄土真宗独自のマナーがあります。
他の宗派では四十九日まで「御霊前」、以降は「御仏前」を表書きとして記入しますが、浄土真宗では時期に関わらず「御仏前」を用います。
即身成仏の教えにより、亡くなった人はすぐに仏へ成れると考えられているためです。
間違えないか不安な方は「御香典」とするのがよいでしょう。
なお、金額の相場は一般的な葬儀と変わりありません。詳しい相場は以下の記事で解説しているため、参考にしてみてください。
【関連記事】家族葬での弔電や香典の正しいマナー【例文付き】送る側と受け取る側
言葉遣い
他の宗派で良しとしていても浄土真宗では不適切とされている言葉があります。
代表的な言葉と、言い換え表現は以下のとおりです。
| 浄土真宗で不適切とされる言葉 | 言い換え |
|---|---|
| 草葉の陰・天国 | お浄土、み仏の国 |
| 天国に行く | 浄土に参る |
| 昇天・他界・永眠 | 浄土に往生する |
| 御霊前・みたま | 御仏前・御尊前 |
| 祈る | 念ずる |
| 冥福を祈る | 哀悼の意を表する |
| 魂・魂魄・御霊 | 故人 |
| 安らかにお眠りください | 私たちをお導きください |
| 黙念 | 合掌・礼拝 |
| 祭壇 | 荘厳壇 |
| 告別式 | 葬儀 |
| 戒名 | 法名 |
上記の言葉に加えて、仏式葬儀で不適切とされる「忌み言葉」も使用しないよう気をつけましょう。
忌み言葉については以下の記事で解説しています。参考にしてみてください。
【関連記事】注意!葬儀で控えるべき「忌み言葉」の一覧と言い換え方を解説
線香
日々のお勤めで使用するお線香の作法も、浄土真宗では少し異なります。
お線香は火元が左側にくるように寝かせて置くのがマナーです。
線香立てに寝かせられない場合は、二つに折っても問題はありません。
【Q&A】浄土真宗に関してよくある質問

浄土真宗に関してよくある質問をまとめました。内容は以下のとおりです。
Q.浄土真宗と浄土宗は何が違うのですか?
Q.浄土真宗が喪中でしてはいけないことはありますか?
ひとつずつ見ていきましょう。
Q.浄土真宗と浄土宗は何が違うのですか?
A.浄土真宗と浄土宗では教義が異なります
<教義の違い>
浄土宗:阿弥陀如来の念仏を熱心に唱えていれば誰でも極楽浄土へ行ける
浄土真宗:阿弥陀如来を信じていれば誰でも極楽浄土へ行ける
浄土宗は法然が開いた宗派で、浄土真宗は法然の弟子である親鸞が教えを発展させて開いた宗派です。
そのため、同じ阿弥陀如来を本尊としていますが、教義が異なります。
Q.浄土真宗が喪中でしてはいけないことはありますか?
A.浄土真宗には忌中・喪中の概念がないため、基本的に「してはいけないこと」はありません。
とはいえ、忌中・喪中は一般的にはお祝い事への参加は避けるべきとされている期間です。
浄土真宗の考え方としては間違っていないものの世間から非常識に見られる可能性もあるため、派手な活動は控えた方がよいでしょう。
まとめ

浄土真宗には、亡くなった方はすぐに極楽浄土へ行けるという「即身成仏(往生即成仏)」の教えがあります。
他の宗派と異なり、故人が極楽浄土へ向かうための旅路期間がないため「供養」は必要ないと考える点が特徴です。
そのため、葬儀は故人を供養する目的ではなく、大切な人の死を通じて阿弥陀様のご加護に感謝するための儀式です。
また、本願寺派・大谷派で式次第も若干異なります。初めて浄土真宗で葬儀を執り行う方は、家の派を把握し、わからない点・不安な部分も適切にサポートしてくれる葬儀社に依頼しましょう。
コープの家族葬では、浄土宗をはじめとしたさまざまな宗教宗派の葬儀に対応しています。
家族葬・1日葬・自宅葬・火葬式プランなど、お客様の都合・予算・ニーズにそった葬儀を提供可能です。
お問い合わせは24時間無料で受け付けているため、気軽にご相談ください。
葬儀ブログの他の記事
-
-
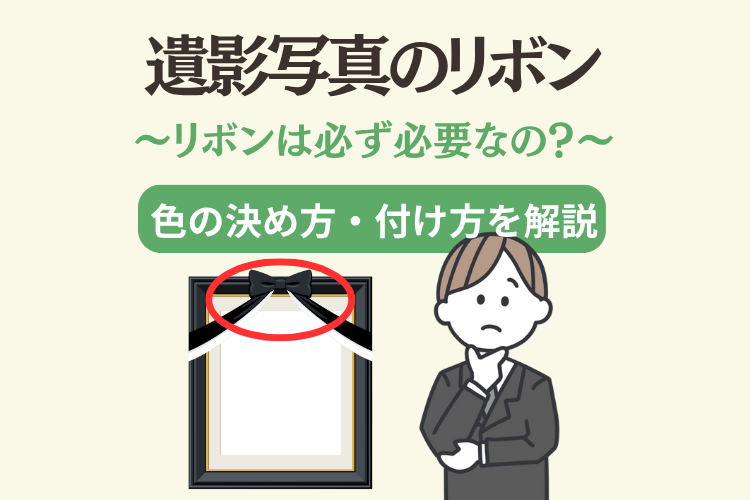
-
【葬儀準備】遺影写真のリボンは必要?色の決め方や付け方を解説
2025/11/30
-
-
-
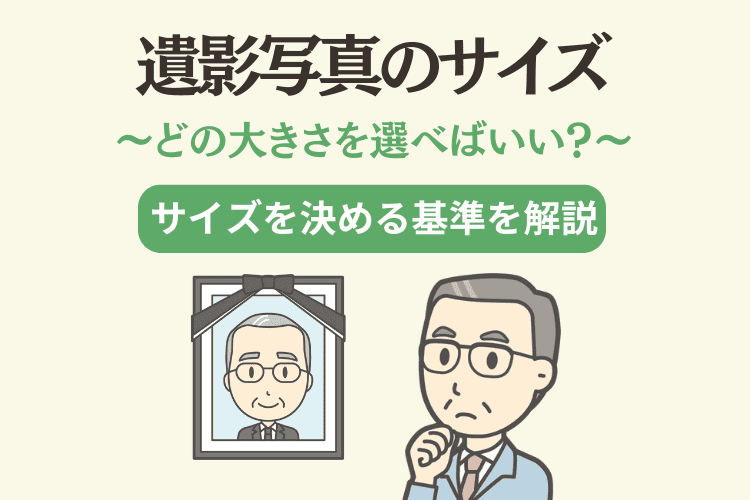
-
遺影写真のサイズと選び方|用途別の一覧表と写真の選定方法を解説
2025/11/29
-
-
-
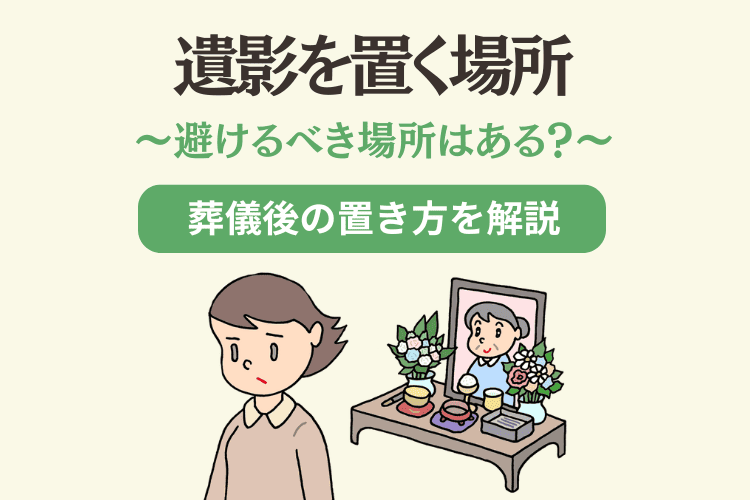
-
遺影の置き場所の正解は?避けるべき場所・注意点・正しい飾り方を解説
2025/11/28
-