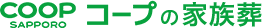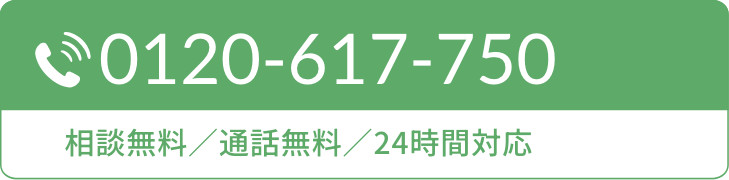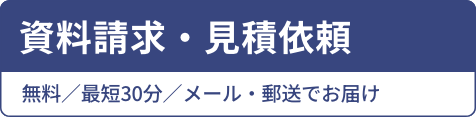お葬式や葬儀後のご供養では、線香やろうそくを使用しますが、線香やろうそくにはどんな意味や役割があるかご存知でしょうか。
お葬式では、お通夜に「寝ずの番」と呼ばれる習慣があり、線香やろうそくを絶やさない古くからのしきたりがあります。
お葬式における作法はとても重要で、不手際やマナー違反があると、親戚から白い目で見られてしまうため、注意しなければなりません。
そこで、線香とろうそくの意味や役割と、知っておくべき線香のあげ方の作法について、ポイントを押さえて分かりやすく解説します。
寝ずの番に関しても、知っておきたい基礎知識や、事前に確認しておくべき注意点やマナーまでご紹介しますので、どうぞ最後までお目通しください。
<この記事でわかること>
- お葬式で線香やろうそくを使用する理由
- 線香の供え方
- お通夜の寝ずの番について
お葬式で線香やろうそくを使用する理由

亡くなった人へ線香やろうそくを使用するのには理由があり、それぞれ意味と役割があるため、詳しく解説します。
線香の意味と役割
仏教では、線香を焚くことによって、心身や周囲を浄化できるといわれており、お葬式での線香には次の3つの役割があります。
- 故人の食べ物になる
- 故人と心を通わせられる
- 空気の浄化と癒しの効果がある
故人の食べ物になる
仏教においては、亡くなった人は香りを食べるという考え方があります。
そのため、お葬式やその後の供養では、線香を焚いたり、炊きたてのご飯や入れたてのお茶をお供えして、煙や湯気を大切にします。
故人と心を通わせられる
亡くなった人へ線香をあげるのには、故人と心を通わせて対話ができる役割があるためです。
また、線香の立ち上がる煙は、あの世とこの世を繋ぐ架け橋になるともいわれています。
空気の浄化と癒しの効果がある
線香には、仏教とは無関係で空気の浄化作用があるため、死臭を抑える効果もあります。
さらに、香りには癒しの効果もあります。大切な人を失った悲しみを和らげ、穏やかな気持ちにさせるのも、線香の一つの役割です。
ろうそくの意味と役割
ろうそくの炎である光明は、人々を照らす仏様の象徴であり、お葬式で使用するのには次の2つの役割があります。
- 道しるべになる
- 救いの智慧
道しるべになる
ろうそくの炎は、あの世とこの世の道しるべになるといわれており、極楽浄土へと旅する故人を照らす役割があります。
お盆に提灯を用意するのは、明かりを灯して、故人が迷わず帰って来られるようにするためです。
救いの智慧
仏教では「光明とは智慧のかたちなり」といわれ、ろうそくの炎には欲や煩悩といった不浄を祓い、迷いの闇から真実へと向かわせてくれる力があるといわれています。
なお、ろうそくは、神道では御霊の慰めとして、キリスト教では生命の象徴として、仏教以外の多くの宗教で用いられています。
線香やろうそくはお葬式後の供養でも必要
線香やろうそくは、仏教で五供(ごくう)と呼ばれる5つのお供え物の一つで、お葬式後のお墓やお仏壇でのご供養でも不可欠となります。
- 香:線香や抹香
- 花(華):生花や造花
- 灯明:ろうそく
- 浄水:水やお茶
- 飲食:ご飯(お米)やお菓子や果物
線香の供え方

線香を供える方法について、知っておきたいポイントを次の3つの順序で解説します。
- 線香をあげる手順
- 宗教による線香の供え方の違い
- 線香をあげる場面
線香をあげる手順
線香のあげるときには作法があり、ろうそくから火をつけることと、炎に息を吹きかけないことがマナーのため、手順をご紹介します。
- ① 数珠があれば左手で軽く握る
- ② 遺影やお位牌に向かって一礼する
- ③ マッチでろうそくに火を灯して、線香をかざして火をつける
- ④ 線香を持った反対ので軽く扇いで線香の火を消す
- ⑤ 香炉にお線香を供える
- ⑥ 仏壇の場合はおりんを鳴らす
- ⑦ 合掌して深く一礼する
- ⑧ ろうそく消しを炎に被せるか、手で仰いで火を消す
宗教による線香の供え方の違い
線香は、同じ仏教でも宗派やお寺によって供え方の作法が異なります。一般的には次のとおりです。
- 真言宗:3本(手前1本・奥2本)真上から見て逆三角形に立てる
- 天台宗:決まりはないが1本または3本
- 浄土宗:1~3本(中央へ立てる)1本を二つ折にして寝かすこともある
- 臨済宗・曹洞宗:1本(中央へ立てる)
- 日蓮宗:1本または3本(手前1本・奥2本)真上から見て逆三角形に立てる・1本の場合は中央へ立てる
- 浄土真宗:1本(二つ折にして寝かせる)
線香をあげる場面
亡くなってからは線香をあげる場面が多くあるため、順を踏まえてご紹介します。
- ① ご遺体を安置してからお通夜まで
- ② お通夜から葬儀の前まで
- ③ お葬式後の自宅での供養・弔問
- ④ 仏壇
- ⑤ お墓参り
① ご遺体を安置してからお通夜まで
病院などからご遺体を搬送して、ご自宅や斎場へ安置する際、一般的に枕飾りを用意して、線香をお供えします。
お葬式の日程を迎えるまでの間に親族や弔問客が訪れた場合は、線香をあげてもらうことが一般的です。
② お通夜から葬儀の前まで
お通夜の日は、棺へご遺体を納棺して斎場へ到着後、お通夜が始まるまでの間に祭壇へ向かって線香をあげることが多くあります。
親族などの参列者は、斎場へ到着したら、遺族へお悔やみを伝えてから線香をあげましょう。
③ お葬式後の自宅での供養・弔問
お葬式が終わると、位牌と遺影と遺骨を配置するために、自宅へ後飾り壇として祭壇を用意します。
四十九日を迎えるまでは、毎朝・毎夕、炊きたてのご飯と新鮮なお水をお供えして、線香をあげて手を合わせてください。弔問客が訪れたら線香をあげてもらいましょう。
④ 仏壇
四十九日法要では、仮の白木位牌から長く使用する本位牌へと交換する必要があるため、本位牌は事前に仏壇と一緒に用意します。
線香をあげるのは、毎朝・毎夕、遺族がやるべき大切なおつとめです。毎日の習慣として、家族揃って心掛けるようにしましょう。
⑤ お墓参り
納骨先となるお墓を用意したら、納骨式により遺骨を納め、その後はお盆や春・秋のお彼岸や一周忌などの命日を中心に、お墓参りをして線香をあげます。
なお、屋外のお墓参り用の線香は、自宅用の線香とは種類が異なり、杉線香と呼ばれる煙の多い線香を用いるのが一般的です。
お通夜の準備や焼香の作法については、「【お通夜のマナー】服装や持ち物からお香典とお焼香の作法まで全解説」「家族葬における焼香のやり方やマナーを解説|焼香だけの参列についても説明」の記事でご紹介していますので、併せてご確認ください。
お通夜の寝ずの番について

お通夜に行う「寝ずの番」について、必要な知識を理解しやすいよう、次の5つの順序で解説します。
- お通夜とは?
- 寝ずの番の意味
- 寝ずの番を行うときの注意ポイント
- 寝ずの番のマナーと作法
- 線香とろうそくの火の持続期間
お通夜とは?
お通夜とは、葬儀の前日に故人の家族や血縁者などの近親者を中心に、故人と最後の夜を過ごす儀式です。
故人の友人や知人、仕事仲間や近所の人たちが遺族へお悔やみを伝える機会でもあり、昔ながらの一般葬では、お通夜へお香典を持参して参列します。
葬儀の規模によっても異なりますが、お通夜は一般的に18~19時頃から開始して、読経のもと身内や参列者がお焼香を執り行い、約1時間程度で終了します。
お通夜が終わると、通夜振る舞いと呼ばれる会食を行い、故人との生前の思い出を語り合います。
近年は夜が更けたら解散する半通夜も増えていますが、地域やご家庭によっては、遺族や近親者が「寝ずの番」を行うこともあります。
寝ずの番の意味
寝ずの番とは、故人が極楽浄土へと無事にたどり着くよう、夜通し冥福を祈りながら、線香とろうそくの炎を絶やさない儀式です。
人は亡くなると、四十九日まで極楽浄土へ向かって旅をして、あの世とこの世の狭間となる冥土と呼ばれる暗黒の地をさまよいます。
初七日には三途の川のほとりへ辿り着きます。悠々と渡ることができる立派な橋を使って川を渡る人もいれば、荒々しい激流の中を渡らなければいけない人もいるとのことで、どの橋を渡るかは生前の行いによって異なります。
7日ごとに行われる法要は、閻魔様等など「十王」と呼ばれる仏(尊格)の裁判のタイミングでもあり、僧侶による読経のもと、故人の冥福を祈ることが古くからの習わしです。
また、かつては意識不明の仮死状態を分別することが難しく、お通夜で亡くなった人が甦ることもあったといいます。
このような経緯からもお通夜は全国的に浸透しましたが、医学が発展した現在は、亡くなった人が蘇生することはほとんどありません。
とはいえ、死後24時間経過しなければ火葬してはならないことは法律で定められており、違反すると1,000円以下の科料または拘留が科せられるため、ご注意ください。
出典:墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)
寝ずの番を行うときの注意ポイント
寝ずの番を行うときは、押さえておくべき4つのポイントがあるため、重要な順にご紹介します。
- 宿泊できるかどうかを確認する
- 誰がやるか交代する人も決めておく
- 何時間を目安にするかを決める
- リラックスできる服を用意する
宿泊できるかどうかを確認する
寝ずの番をやりたくても、利用する斎場や条件によっては夜間の利用や、宿泊ができない可能性があるためご注意ください。
葬儀社へは、線香やろうそくの使用ができるかどうかも併せて事前に確認しておきましょう。
また、一般的に宿泊できる人数には限りがあります。レンタルによる貸し布団の場合、事前予約が必要なため、手配も忘れないようにします。
誰がやるか交代する人も決めておく
寝ずの番にあたっては、誰がやるか、交代する相手も含めて、事前に打ち合わせて決めておきましょう。
誰がやるべきという決まりはとくにありませんが、一般的には家族や故人の血縁者にあたる兄弟姉妹などか行うケースが多いです。
住み慣れた自宅なら安心ですが、斎場などの不慣れな環境で、夜な夜な起きて一人で寝ずの番をするのは不安があると思います。
とくに喪主は、看病や葬儀の準備、翌日の葬儀・告別式に向けても疲労が蓄積しやすい時期でもあります。
さらに、寝ずの番は線香やろうそくの火気を使うため、火事を起こさないように気を付けなければなりません。
無言で線香の煙や、ろうそくの炎を見つめていると睡魔に襲われる可能性も高いため、うっかり寝てしまわないように、2人体制などで対応するのが最良です。
可能であれば、喪主の負担を軽減するためにも、喪主の兄弟姉妹や子どもたち、もしくは故人の血縁者が協力するようにしましょう。
何時間を目安にするかを決める
寝ずの番にあたっては、何時間ずつにするか、人数を決めて対応しましょう。
たとえば、4時間ずつの2交代制の場合、23時から開始として、深夜3時頃に交代することになります。
熟睡できないと寝不足になってしまうため、お葬式の前後は仮眠をして休息するようにしてください。
なお、寝ずの番では、もし眠ってしまったとしても問題はありません。故人が地獄に堕ちることもないため、注意するのは火気のみと思ってください。
リラックスできる服を用意する
お通夜では喪服を着用するのが一般的ですが、寝ずの番にあたってはリラックスできるジャージやスウェットなどのルームウェアを用意するのがおすすめです。
喪服は、翌日も葬儀・告別式で着用することもあり、シワにならないようにしましょう。
また、葬儀場や日程によっては、他の利用者が同じように寝ずの番をして過ごす可能性もあるため、華美な服装は避けるようにご注意ください。
斎場によっては、宿泊施設が完備されており、バスルームで疲れを癒して、寝室や休憩室で布団を敷いて休むことができます。
アメニティ用品やメイク道具などの持ち物も忘れないようにご持参ください。
一部の良心的な斎場では、ドライヤーや髭剃りや歯ブラシ、スキンケア用品なども用意されているため、事前に確認しておくと安心です。
遺族の立場では、葬儀後も挨拶廻りやさまざまな死後の手続きなどがあり、忙しい日々が続くため、無理なく体力の温存を大切にしましょう。
寝ずの番のマナーと作法
寝ずの番にあたって、注意するべきマナーと作法のポイントは次の5つです。
- ろうそくと線香は1本ずつ使用する
- 線香はろうそくから火をつける
- 線香の火は反対の手で仰いで消す
- ろうそくの炎はろうそく消しを使用して消す
- 安全を最優先にする
線香が燃え尽きそうになったら次の線香へ、ろうそくから火をつけてお供えするのが、寝ずの番の基本的な流れです。
ろうそくは短くなったら、火のついた古いろうそくを上に取り外し、新しいろうそくを差して火を移し、手で仰いで炎を消しますが、決して無理しないでください。
完全に燃焼してから新しいろうそくを利用するか、ろうそく消しを使用して熱が冷めてから、新しいろうそくへ交換した方が安全でスムーズです。
一番大切なのは安全性のため、寝ずの番では無理することのないようにご注意ください。
線香とろうそくの火の持続期間
種類によっても異なりますが、一般的に葬儀で用いる線香とろうそくの火の持続時間は、次のとおりです。
- 線香:約30分
- ろうそく:約5時間
ただし、葬儀社によっては、遺族が交換をしなくても済むように、12時間程度もつ渦巻き線香や、24時間持続する耐久時間の長いろうそくを使用することも多くあります。
また、安全性を考慮した電気タイプの線香やろうそくもあり、火気を使用しない方法もあるため、事前に確認しておくようにしましょう。
なお、お葬式では親戚と揉め事になるケースもあるため、「家族葬の親戚トラブル事例7選!トラブルを防ぐ対策と対処法をご紹介」の記事で事前に注意事項を確認しておくと安心です。
まとめ:線香とろうそくはお葬式後も必需品のためマナーを知っておこう!

お葬式に使用する線香とろうそくの意味や役割と、お葬式の「寝ずの番」の知識やマナーについてご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。
- お葬式で使用する線香やろうそくは、仏教の供養で必要な五供にあたり、故人が極楽浄土へたどり着けるようにする役割がある。
- 線香やろうそくの火は息を吹きかけずに手で仰いで消化するか、ろうそく消しを使用するのがマナー。線香のお供え方法は、宗派によって本数やあげ方が異なる。
- 寝ずの番にあたっては、事前に葬儀社へできるかどうかを確認して、誰がやるか交代する人を含めて決めておき、リラックスできる服装を用意する。
- お葬式後も線香やろうそくは必要となり、仏壇やお墓参りの供養で使用するため、作法を知っておくと良い。
コープの家族葬では、家族やご親戚の皆さまが快適に過ごせる斎場をご紹介。人目を気にせずお葬式ができる「貸し切り」に対応する施設や、「飲食の持ち込み」が可能な施設があります。
バスルーム付きの宿泊施設には、便利なアメニティ用品もご用意。ソファーやテレビも完備しているため、寝ずの番も寛ぎながら行えるとたいへん評判です。
各斎場では定期的に見学会や事前相談会を実施しているため、ぜひ足を運んでいただければと思います。ご自宅でのお葬式も可能なため、お気軽にご相談ください。