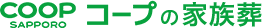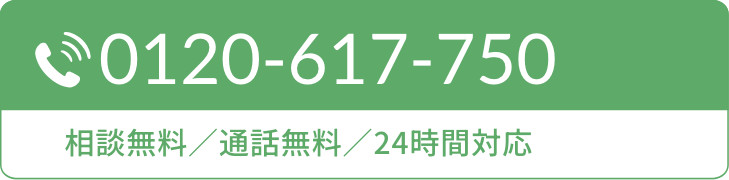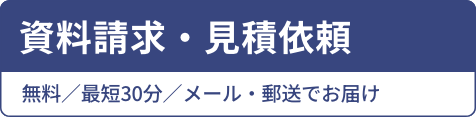「家族葬は何親等まで参列してもらうのが正解?」
「声をかけなかった親族から不満を言われることはある?」
家族葬は一般的な葬儀のように、故人とゆかりのあった方々が集まる形式ではありません。参列する方は遺族の方で決定します。
そのため、どこまで呼んだ方がよいのか、と不安になる遺族も少なくありません。
そこで、本記事では家族葬に参列する親等の一般的な範囲や、参列者の決め方などを解説します。参列を辞退してもらう方への報告方法なども紹介していますので、家族葬を検討している方は参考にしてみてください。
そもそも「家族葬」とは

「家族葬」とは、遺族や近しい親族のみで執り行う小規模な葬儀を指します。
近年増加傾向の葬儀形式であり、小規模で行うため、故人とゆっくりお別れができる点がメリットです。流れは通常の葬儀と変わりありません。1日目に通夜、2日目に告別式と火葬を執り行います。
家族葬が増えている理由としては、以前よりも地域とのつながりが希薄になってきていることや、現代の方々が昔ながらの慣習よりも気持ちを重んじるようになってきた傾向が強いためとされています。
また、新型コロナウイルスによる小規模葬へのニーズ増加も関係しているようです。
家族葬には何親等まで参列してもらうべき?

家族葬へ参列してもらう方に明確な定義はありません。ただし、二親等まで声をかけるのが一般的とされています。
二親等とは、祖父母や孫までの範囲です。広くても六親等まで声をかければ十分と言えるでしょう。なお、民法においては、配偶者・血族6親等・姻族3親等までが「親族」と定められています。
参考:民法第725条
家族葬に参列してもらう人数の決め方

家族葬に参列してもらう人数や範囲を決めかねている場合は、以下の基準を参考にしてみてください。
- 原則は故人の遺志に従う
- 葬儀場の規模を基準にする
- 故人との関係性によって決める
- 家族葬を執り行った親類のアドバイスを参考にする
なお、それでも参列してもらうか迷った場合は、声をかけておく方が無難です。それぞれ解説します。
原則は故人の遺志に従う
生前、故人が参列して欲しい方々をリストアップしている場合は、故人の遺志に従うのが原則です。
「自分の葬儀は家族葬がいい」と考えている方は、エンディングノートなどに参列して欲しい方の名前と連絡先を記載しておくと、逝去後に参列者へ連絡する遺族の負担が軽くなります。
葬儀場の規模を基準にする
葬儀場には、ある程度収容できる人数の限界が定められています。そのため、会場の規模を基準として参列者を決めるのもよいでしょう。
以下は、参列者の人数別でどこまでの親族に声をかけるかをまとめた一般的な表です。
| 参列者の人数 | 声をかける親族の範囲 |
|---|---|
| 〜5名 | 故人の配偶者と子ども |
| 〜10名 | 故人の配偶者、子どもとその家族 |
| 〜20名 | 上記の範囲に加え、故人の兄弟・姉妹 |
| 〜30名 | 上記の範囲に加え、故人のいとこ・甥・姪 |
| 30名以上 | 上記の範囲に加え、故人が親しくしていた友人 |
家族葬の場合は30名以内にとどめるのが一般的です。しかし、会場が対応可能であれば、30名以上の家族葬になっても問題はありません。
故人との関係性によって決める
前述の通り、家族葬には参列してもらう範囲に厳密な決まりはありません。
そのため、家族以上の付き合いがあった方や、故人が大変お世話になった方がいる場合は、親族でなくても参列可能です。「故人が最後に会いたい人は誰か」を基準に参列者を決めてあげましょう。
家族葬を執り行った親類のアドバイスを参考にする
故人の遺志がなく、交友関係も把握していない場合は、家族葬を執り行った経験のある親類にアドバイスをもらう方法もあります。
親類であれば「自分のときはあの人まで呼んだ」「あの人は声をかけた方がよいと思う」など、より具体的な助言が受けられる可能性もあります。
家族葬へ参列してもらう方への連絡方法

家族葬へ参列してもらう方への連絡方法や、連絡のタイミングは以下のとおりです。
- 訃報は電話で知らせる
- 葬儀の日程は電話またはメールで知らせる
それぞれ解説します。
訃報は電話で知らせる
訃報の連絡は電話で知らせるのがマナーです。病院などから逝去の連絡を受けたら、故人と血縁が近い方などにはすぐに電話で訃報を伝えましょう。
また、参列してもらう・もらわないに関係なく、故人や自分が所属している会社には連絡しなければなりません。逝去に際する諸手続きがあるためです。
葬儀の日程はメールなどで知らせる
葬儀の日程が決まったら、参列していただきたい方々へ改めて詳細を報告します。最適な方法は電話ですが、メールでも問題はありません。
近年は、親しい間柄であればLINEなどのSNSを用いる方も増えています。香典や供花を辞退する場合は、その旨も一緒に伝えましょう。
参列を辞退してもらう方への連絡方法

参列を辞退してもらう方へは、葬儀を執り行ったあとに訃報連絡をするのが一般的です。
しかし、なかには訃報をあとから聞いて「なんで早く教えてくれなかったのか」「自分も参列したかった」と不満を言う方も少なくありません。そのような可能性のある方々には、事前の連絡が必要です。
本章では、参列を辞退してもらうが事前に訃報連絡をする場合と、一般的な葬儀後の報告と、2つの連絡方法を紹介します。内容は以下のとおりです。
- 事前に伝える場合は会葬辞退の案内を出す
- 家族葬を執り行ってから訃報連絡とともに伝える
それぞれ解説します。
事前に伝える場合は会葬辞退の案内を出す
事前に伝える場合は、会葬辞退の案内を出します。書面でもよいですし、電話でも問題はありません。
訃報連絡をする際に、家族葬であること、参列は控えていただきたい旨を丁寧に伝えましょう。事前に意向を伝えておけば、ほとんどの人は遺族の気持ちを尊重し、参列は辞退してくれます。
家族葬を執り行ってから訃報連絡とともに伝える
事前に連絡した方以外は、家族葬を執り行った後に報告します。タイミングは四十九日以降が一般的です。年末が近い場合は、喪中ハガキなどを代替としても問題はありません。連絡手段は手紙や電話を用います。
事後報告には、以下の内容を盛り込むようにしましょう。
- 亡くなった事実と逝去の日
- 生前お世話になったことへのお礼
- 家族葬にて身内のみでとり行った旨
- 事後報告になったことへの謝辞
弔問や香典を辞退する場合は、この報告で伝えます。
家族葬に参列する際のマナー

たとえ遺族だけの小さな家族葬であっても、マナーには配慮が必要です。本章では、なかでも大切な身だしなみと香典に関するマナーを解説します。
服装
家族葬であっても、遺族は正喪服を着用します。参列者の場合は準喪服を着用するのがマナーです。お子さんは学校制服が礼服に該当するため、ある場合は着用しましょう。無い場合は黒に近い落ち着いた色合いの服を選ぶとよいでしょう。
メイクはナチュラルにし、結婚指輪以外のアクセサリーは控えます。長い髪は一つに束ねて清潔感を心がけましょう。男性はクセや寝癖を整える程度に留めます。髪がテカテカになるほどワックスをつけるのはマナー違反です。
香典
香典辞退の意向がある場合は、参列するしないにかかわらず香典を包まないのがマナーです。どうしても形で弔意を伝えたい場合は、供花を送るとよいでしょう。ただし、供花も辞退している場合、無理に送るのはマナー違反となります。
香典を包む場合は、一般的な葬儀のマナーと変わりはありません。白黒の水引が印刷されている香典袋や、水引がかかっている封筒に「御香典」と記載し、下の段に自分の名前を記載します。包んだ金額は漢数字で書くのがマナーです。
家族葬への参列に関してよくある質問
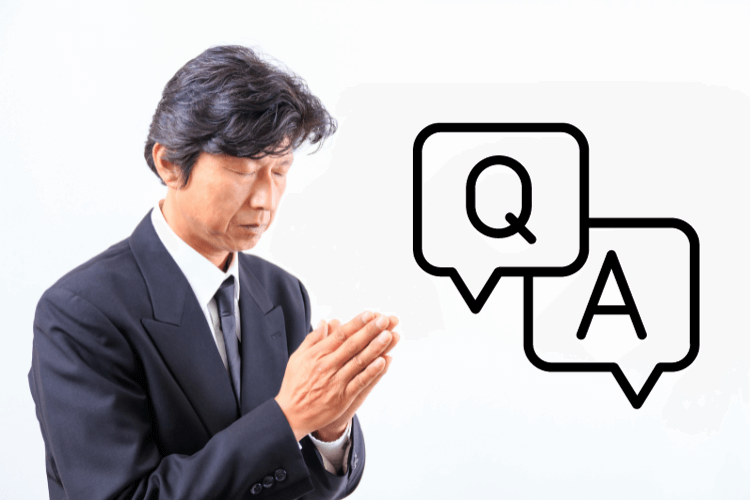
家族葬への参列に関してよるある質問をまとめました。内容は以下のとおりです。
Q.家族葬と言われた場合、お通夜に参列するのは迷惑?
Q.家族葬で会葬辞退を伝えたのに参列したいと希望された場合はどう対応すればいい?
Q.忌引休暇を使えるのは何親等まで?
Q.家族葬に呼ばれなかった場合でも香典は送っていい?
ひとつずつ回答します。
Q.家族葬と言われた場合、お通夜に参列するのは迷惑?
家族葬の連絡を受けた際に「会葬辞退」などの言葉がなければ参列しても問題はありません。
「会葬を辞退しますと伝えられたがどうしても参列したい」という場合は、遺族に直接確認するのがよいでしょう。連絡せずに参列するのは遺族に迷惑がかかってしまうため、必ず事前に確認しましょう。
Q.家族葬で会葬辞退を伝えたのに参列したいと希望された場合はどう対応すればいい?
改めて、「家族葬であること、今回は家族だけで見送りたい意思があること」を丁寧に伝えます。もしも突然葬儀場に来てしまった場合は、一緒に故人を見送ってもらいましょう。
Q.忌引休暇を使えるのは何親等まで?
一般的には三親等までが忌引き休暇をもらえるとされています。しかし、会社によって規定が異なるため、不安な場合は事前に確認しておくとよいでしょう。
Q.家族葬に呼ばれなかった場合でも香典は送っていい?
香典を送る行為自体は問題ありません。しかし、香典辞退の意向を聞いているにもかかわらず送るのはマナー違反です。
まとめ:家族葬へ参列してもらう方に特定の決まりはない
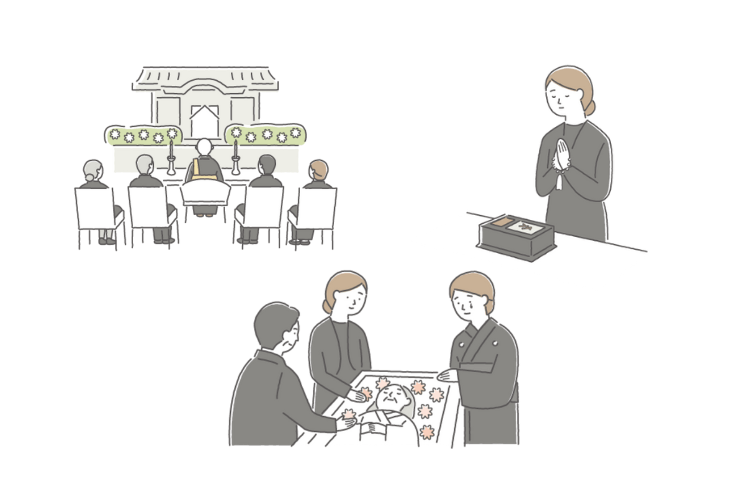
家族葬の参列者には「何親等まで」のような決まりは存在しません。故人の遺志や葬儀場の規模を基準に決めるとよいでしょう。それでも迷う場合は、家族葬を執り行った経験のある親族にアドバイスをもらう方法もあります。
親族のなかで呼ぶ人・呼ばない人を分ける場合は、後々のトラブルを回避するためにも事前に「家族葬であること、参列は辞退したい旨」を伝えて理解を得るとよいでしょう。
コープの家族葬では、少人数から対応可能な家族葬のプランを用意しています。家族葬に関する相談も無料で承っているため、不安や心配ごとがある方はぜひご相談ください。
事前に家族葬について知りたい方には、無料で「お葬式の資料」も用意しています。以下のページから簡単に申し込めるため、興味のある方はぜひお取り寄せください。