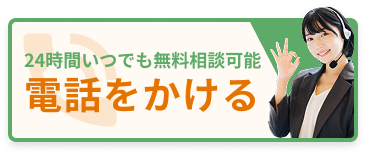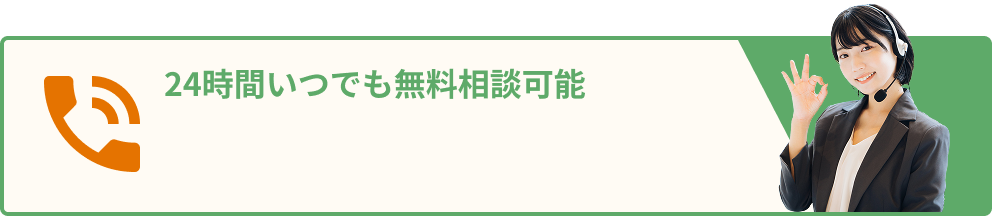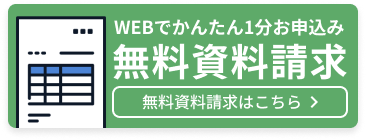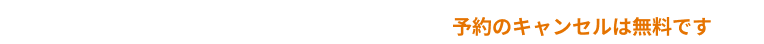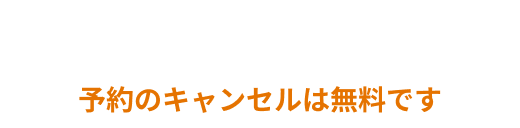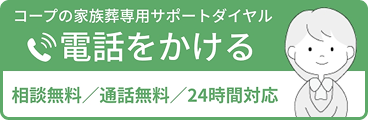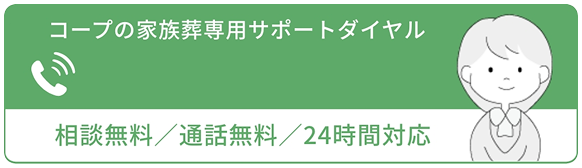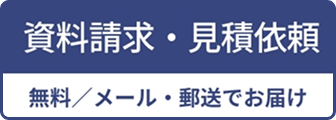葬儀に参列する範囲は?出席を決める基準や葬儀のマナーを解説
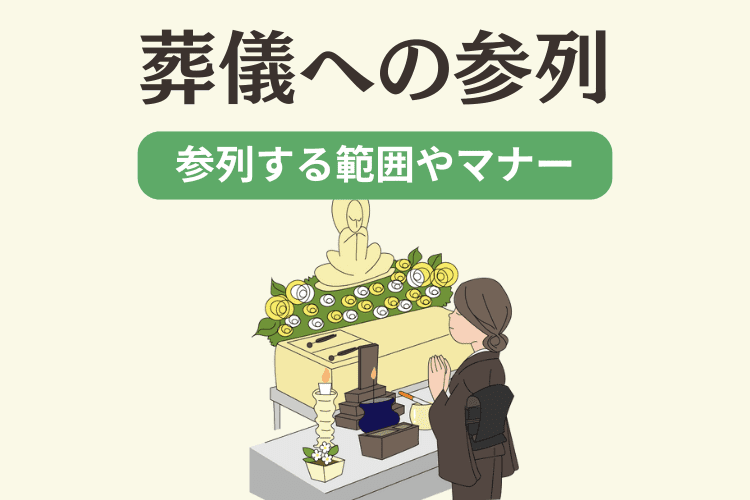
「訃報連絡を受けたけれど、自分は参列するべきだろうか」
「参列する際は、どのようなことに気をつけたらいい?」
葬儀に参列する範囲に決まりはないものの、行くべきか否かと迷う方は少なくありません。
また、参列すると決めた際「服装はどうする?」「香典ってどう用意したらいい?」「焼香の作法が分からない」といった方もいらっしゃいます。
そこで本記事では、葬儀に参列する一般的な範囲や葬儀のマナーについて解説します。
葬儀へ参列するべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
|
<この記事でわかること> ・葬儀に参列する範囲 ・服装のマナー ・身だしなみのマナー ・香典のマナー ・供花・供物のマナー ・挨拶のマナー ・焼香のマナー |
葬儀に参列する範囲はどこまでが一般的?

葬儀に参列する範囲に法律的な決まりはありません。一般的には以下の基準で判断します。
- 血縁関係で決める
- 生前の関係性で決める
- 葬儀形式で決める
ご遺族から訃報を受けた際は、上記の基準を参考に参列するかを決めるとよいでしょう。ひとつずつ解説します。
血縁関係で決める
一般的に三親等以内は参列した方がよいとされています。三親等の範囲は以下のとおりです。
| 三親等の範囲 | |
|---|---|
| 一親等 | 父・母・子 |
| 二親等 | 祖父・祖母・兄弟・姉妹・孫 |
| 三親等 | 甥・姪 |
自身が四親等以上であれば、以降で紹介する「生前の関係性で決める」「葬儀形式で決める」を基準にするのもよいでしょう。
生前の関係性で決める
故人と生前どのような関係性であったかも、参列を決めるうえで大切なポイントです。
「長年親しくしていた」「家族ぐるみの付き合いがあった」などの場合は参列して手を合わせると故人も喜ぶでしょう。
葬儀形式で決める
葬儀形式を考慮して参列するかを決める方法もあります。
通夜を行わない「1日葬」、小規模で執り行う「家族葬」など、形式によって規模や流れが異なるためです。
本項では、以下3つの形式に分けて、参列する目安を解説します。ただし、いずれの場合も「葬儀は家族のみで執り行います」といった参列辞退の意思を伝えられた際は、参列は控えましょう。
- 1日葬
- 家族葬
- 火葬式(直葬)
ひとつずつ見ていきましょう。
1日葬
1日葬とは、通夜を省き、葬儀・告別式のみを執り行う形式です。
両親・配偶者・三親等以内の親しい親族などが参列の目安とされています。
家族葬
家族葬とは、遺族や親族のみで小規模にゆっくりお別れをする形式です。
両親・配偶者・子ども・孫などの近親者が参列の目安とされています。
しかし、「家族葬」=「家族だけ」ではないため、仲のよかった友人や、お世話になった方が参列するケースもあります。
【関連記事】家族葬は家族だけの少人数でも可能?参列する範囲や流れ・マナーを解説
火葬式(直葬)
火葬式(直葬)とは、通夜や告別式といった宗教儀礼をせず、火葬のみで終了とする形式です。
一般的には、両親・子ども・兄弟姉妹など、二親等以内の身内が参列します。
そもそも葬儀の「参列」と「列席」の違いとは

弔事の場では「参列」「列席」「弔問」など、さまざまな言葉を使用します。
「参列」とは何を指す言葉なのか、分からず使用している方もいるでしょう。
弔事でよく使用される言葉の種類と意味は、以下表のとおりです。
| 弔事の場でよく使用される言葉 | |
|---|---|
| 参列 | 意味:特定の式典などに出る
用途:招かれた自分を指す際に使用 |
| 列席 | 意味:列(式典などの列)に加わる
用途:主催者側が、式に出た人を指す場合に使用 |
| 出席 | 意味:大人数が集まる会合に出る
用途:式に出る場合に使用 |
| 参加 | 意味:特定の集まりのなかに加わる
用途:葬儀の場では使用する機会はほとんどない |
| 弔問 | 意味:遺族の元を訪ねてお悔やみを述べる
用途:葬儀当日ではなく後日訪ねる場合に使用 |
特に「参列」と「列席」はよく使用されます。自分が使用する際に、意味を間違えないよう注意しましょう。
以降では、「参列」と「列席」の意味・使い方・例文を紹介します。
参列とは
「参列」は、儀式・式典などに出席することを意味し、招かれたほうを指す言葉として使われます。そのため、葬儀に参加する方を「参列者」とも呼びます。
喪主や遺族は「お招きした側」に該当するため、遺族に対して「葬儀に参列する」と言うのは間違いです。
| <参列の例文>
・お通夜に参列させていただきます。 ・葬儀に参列できず、申し訳ありませんでした。 |
列席とは
「列席」も、参列と同じく儀式・式典へ出席することを指しますが、使用できる人が限られます。
参列は誰でも使用できる反面、列席は主催者(喪主・遺族)が参加者を指す際にしか使用しません。葬儀の場では、主に挨拶などで用いられます。
| <列席の例文>
・ご列席のみな様、本日はお忙しいなか足を運んでいただきありがとうございました。 ・ご列席のみな様には、簡単ではございますがお食事の席を用意しております。 |
服装のマナー

葬儀に参列する際は、基本的に男女ともに喪服を着用します。参列者は喪主より一つ格式の低い礼服を着用するのがマナーです。
喪主は正喪服を着用するため、参列者は準喪服を選択しましょう。
以降では、以下の立場に分けて服装のマナーを解説します。
- 男性の場合
- 女性の場合
- 子どもの場合
ひとつずつ解説します。
男性の場合
男性は、礼服用のブラックスーツを着用するのがマナーです。
ネクタイ・ベルトは黒色にします。ベルトはバックルが目立たないシンプルなものを選びましょう。
ワイシャツは白無地で、カフスボタンやネクタイピンは使用しません。
結婚指輪以外のアクセサリーは外します。時計が必要な場合は、華美なデザインを避け、シンプルなものを選びましょう。
靴下・靴は黒色で、フォーマルな革靴を着用します。
【関連記事】初めての葬儀に備える服装のマナー|性別・年齢別で注意点を解説
女性の場合
女性は、ワンピースやアンサンブルタイプのブラックフォーマルを着用します。パンツスタイルでも問題はありません。
インナーは黒のカットソーまたは白いブラウスが最適です。
結婚指輪以外のアクセサリー類はすべて外しますが、真珠のネックレスやイヤリングは許容範囲です。
黒色のストッキングと、黒いパンプスを着用しましょう。
【関連記事】初めての葬儀に備える服装のマナー|性別・年齢別で注意点を解説
子どもの場合
子どもは、学校指定の制服を着用します。リボンやネクタイに色がついていても問題はありませんが、気になる場合は外しましょう。
制服がない年齢の子は、白いシャツに黒いズボン・スカートなどのシンプルな装いを心がけます。
葬儀は長時間にわたるため、落ち着いた印象をあたえつつも子どもに負担のかからない服を選びましょう。
乳幼児の場合は、それほど気にする必要はありません。落ち着いた色であれば基本的になんでもよいとされています。
大学生は、大人と同じように喪服を着用しましょう。
【関連記事】初めての葬儀に備える服装のマナー|性別・年齢別で注意点を解説
身だしなみのマナー

髪型やメイクなどの身だしなみに配慮するのも、葬儀に参列するうえでは大切なポイントです。特に以下の4点に留意しましょう。
- 髪型
- 持ち物
- メイク
- ネイル
ひとつずつ解説します。
髪型
葬儀では、シンプルで清潔感のある髪型を意識します。髪をまとめる際は、黒色のヘアゴムを使用します。
整髪料は香りの少ないものを選びましょう。明るすぎる髪色の場合は、暗い色に染めるのが理想です。
持ち物
葬儀の際には、以下の持ち物が必須です。
- 葬儀用のバッグ
- 袱紗(ふくさ)
- ハンカチ
- 数珠
葬儀用のバッグは、スーツ店などで販売されています。
袱紗は香典を包むために必要です。色によって使用場面が決められており、弔事の場では紺・緑・グレーなどの寒色を使用します。紫は慶弔どちらにも使えるため、一つ持っておくと便利です。
ハンカチは黒か白の無地を選びます。数珠は自分の宗派にならったもので問題はありません。
メイク
葬儀では「片化粧」と呼ばれる控えめな化粧をするのが基本です。ベージュを基調としたナチュラルなメイクを心がけましょう。
ラメ入りのアイシャドウやチーク、派手な色の口紅は避けた方がよいです。
ネイル
葬儀に参列する際、ネイルはなるべく落としていきます。爪の保護を目的としている方は、クリアやベージュ系などナチュラルな色を選びましょう。
どうしても落とせない場合は、葬儀用の黒い手袋を着用します。
香典のマナー

香典とは、身内の逝去にあたって出費が増える遺族を支える目的で包む金銭です。細かなマナーがあるため、前もって確認しておきましょう。
- 表書きの書き方
- 包む金額
- 受付での渡し方
- 現金書留で送る場合
ひとつずつ解説します。
表書きの書き方
香典袋は、白黒または双銀の水引が描かれている(掛けてある)ものを使用します。水引は結び切りを選びましょう。
表書きは「御香典」または「御霊前」とするのが一般的です。なお、浄土真宗は「御霊前」が使用できないため、「御香典」または「御仏前」とします。
水引の下にフルネームを記載し、中袋の裏面に金額・氏名・住所を記載します。
神式の場合は「御玉串料」「御榊料」、キリスト教の場合は「御花料」と書くのが一般的です。
包む金額
「4」「9」から始まる金額を包むのは避けましょう。「死」「苦」を連想させ、縁起が悪いとされています。
また、新札は不幸を予兆していたと捉えられるため、使用済みのお札を包むのがマナーです。
なお、包む金額の相場は以下のとおりです。
| 香典の金額相場 | |
|---|---|
| 親 | 5〜10万円 |
| 兄弟 | 3〜10万円 |
| 祖父母 | 1〜5万円 |
| 友人・知人 | 5千円〜1万円 |
より詳しい金額を知りたい方はコチラ
受付での渡し方
香典はお通夜や告別式の際に持参します。会場の受付にて「この度はご愁傷様でございます」など一言添えつつ渡しましょう。渡す際は、受付係から表書きが読める向きにします。
なお、香典は差し出す直前まで袱紗に包んでおくのがマナーです。
現金書留で送る場合
どうしても葬儀に参列できないときは、現金書留で香典を送る方法もあります。
現金書留で送る場合は、送り先が喪主となります。葬儀場へ直接送る際は「葬儀場名+”気付”+喪家名+喪主名+”様”」と書きましょう。
なお、香典だけでなくお悔やみの手紙も一緒に送るのがマナーです。
葬儀に間に合わない場合は、葬儀後1週間程度を目安に送ります。
【関連記事】家族葬の場合に香典袋を現金書留で送る際のマナー|送るタイミングや挨拶状の書き方を解説
供花を用意する際のマナー

故人と親しい間柄であった場合は、葬儀に供花を贈ることもあります。お通夜開始の2〜3時間前までには届くよう手配しましょう。
手配方法はさまざまですが、おすすめなのは式場に直接依頼する方法です。式場であれば、祭壇の雰囲気・規模・式場の広さなどの兼ね合いを見て適切な供花を用意できます。
【関連記事】通夜や葬儀に贈る供花の金額相場・手配方法・マナーを宗教別に解説
供物を用意する際のマナー

供花同様、故人と生前親しくしていた場合、供物を贈ることもあります。
贈るタイミングは、供花と同じように開式の2〜3時間前までに届いているのが理想です。宛名は故人ではなく喪主とします。
長期間保存できるものがよいとされており、個包装されたお菓子や、故人が生前好んでいたお菓子などがよく選ばれています。
遺族・親族への挨拶のマナー

遺族・親族への挨拶や声がけにも配慮が必要です。大切な身内を亡くした気持ちに配慮し、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
葬儀の場において長話は必要ないため、「この度はご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」など、代表的なお悔やみ言葉のみで十分です。
また、挨拶する際には以下のマナーにも配慮しましょう。
- 「忌み言葉」は使用しない
- 死因を尋ねるのは避ける
ひとつずつ解説します。
【関連記事】【文例あり】葬儀で遺族にかける「お悔やみ言葉」の種類とマナー
「忌み言葉」は使用しない
葬儀では「使用してはいけない」とされている「忌み言葉(いみことば)」があります。
縁起の悪さから使用を控えるべきとされているもので、代表的なのが以下表の言葉です。
| 葬儀で使用してはいけ「忌み言葉」 | |
|---|---|
| 直接的な言葉 | 死ぬ・急死・生きていた・生存中 |
| 重ね言葉 | 重ね重ね・いろいろ・度々・次々・くれぐれも・重々
※不幸が重なるとされている |
| 不幸の連続を連想 | 再び・また・続いて・追って・引き続き |
| 「不吉」を連想 | 切れる・終わる・数字の”4”と”9” |
上記の言葉は、遺族や親族を不快にさせる可能性があるため、参列時の使用は控えましょう。
【関連記事】注意!葬儀で控えるべき「忌み言葉」の一覧と言い換え方を解説
死因を尋ねるのは避ける
葬儀の場で故人の死因を尋ねるのはタブーとされています。
遺族の口からは言いにくい死因の場合もあるためです。遺族・親族への思いやりを大切にし、説明があるまで待ちましょう。
数珠のマナー

仏式の葬儀には必ず数珠が必要です。あの世へ気持ちを伝えるための大切な仏具のため、葬儀の最中は常に左手首へかけておきましょう。合掌時は親指と人差し指の間に数珠をかけて拝みます。
数珠は魔除けのお守りとしての役割もあるため、貸し借りは厳禁です。必ず自分の数珠を用意しましょう。
なお、焼香時のマナーは以降で解説します。
【関連記事】数珠の持ち方や合掌時の掛け方は?葬儀における数珠のマナーを解説
焼香のマナー

お通夜や、葬儀・告別式では読経の合間に焼香をします。作法は以下のとおりです。
| 1.数珠を左手に持つ
2.右手の人差し指・中指・親指で抹香をつまむ 3.額(ひたい)の高さまで持ち上げる 4.抹香を火種の方に落とす 5.手を合わせる |
上記「3.4.」は宗派ごとに以下の回数が定められています。
| 宗派別・焼香の回数 | ||
|---|---|---|
| 浄土宗 | 1回~3回
一般的には3回行う家が多い |
|
| 浄土真宗本願寺派 | 額に押しいただかず1回 | |
| 浄土真宗大谷派 | 額に押しいただかず2回 | |
| 浄土真宗高田派 | 額に押しいただかず3回 | |
| 臨済宗 | 額に押しいただかず1回 | |
| 日蓮宗 | 額に押しいただかず1〜3回 | |
| 曹洞宗 | 1回目は額に押しいただく
2回目は押しいただかない |
|
| 天台宗 | 1回~3回
特に決まりはない |
|
| 真言宗 | 3回 | |
故人の宗派が分からない場合は、自分の宗派に合わせて問題ありません。
【関連記事】家族葬における焼香のやり方やマナーを解説|焼香だけの参列についても説明
【Q&A】葬儀への参列に関してよくある質問

葬儀への参列に関してよくある質問をまとめました。
Q.葬儀への参列を辞退する場合はどう伝えればいい?
Q.参列できない際に弔意を伝える方法はある?
ひとつずつ回答します。
Q.葬儀への参列を辞退する場合はどう伝えればいい?
A.すぐに電話で連絡するのがマナーです。
ただし、遺族が忙しく電話に出れない場合もあるため、つながらない時はメールで一報いれましょう。メールで伝えた際は、あらためて電話で欠席の旨を伝えます。
辞退の文章は簡単で問題ありません。「本来はご葬儀に伺うべきところですが、体調不良により叶わず残念です」のような内容で十分伝わります。
Q.参列できない際に弔意を伝える方法はある?
A.弔電でお悔やみを伝える方法があります。
NTTの電報へ前日の19時までに申し込めば、全国どこへでも配達可能です。
まとめ:葬儀に参列する際は基本的なマナーを把握しておきましょう

葬儀に参列する範囲にさだめはありません。故人との関係性・交友関係・葬儀の規模などを考慮して、参列するかを決めましょう。
また、参列する際は服装・身だしなみ・持ち物・言葉遣い・所作など、さまざまな点に配慮が必要です。
すべてを完璧にする必要はありませんが、遺族・親族・その他の参列者が不快な思いをしないためにも、基本的な知識は身につけておきましょう。
葬儀ブログの他の記事
-
-
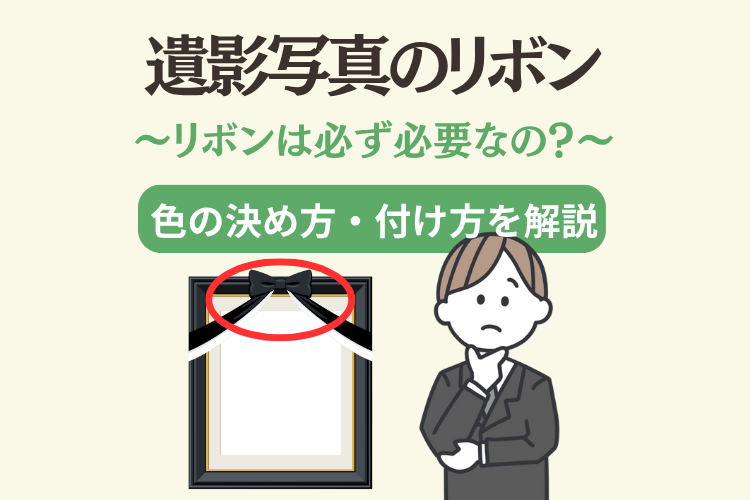
-
【葬儀準備】遺影写真のリボンは必要?色の決め方や付け方を解説
2025/11/30
-
-
-
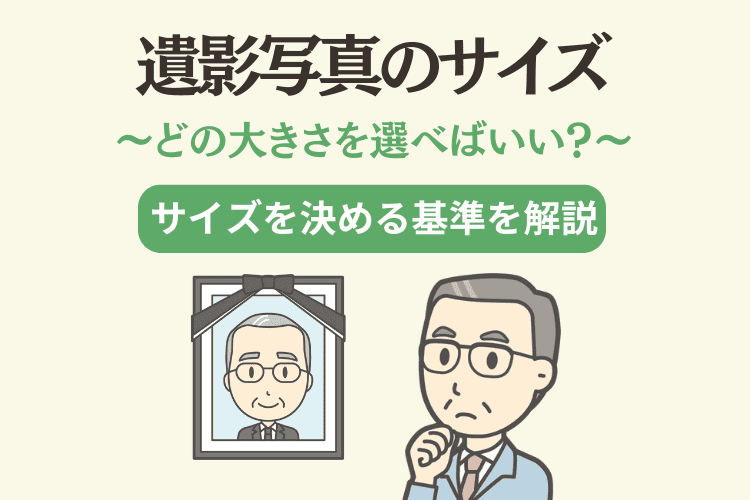
-
遺影写真のサイズと選び方|用途別の一覧表と写真の選定方法を解説
2025/11/29
-
-
-
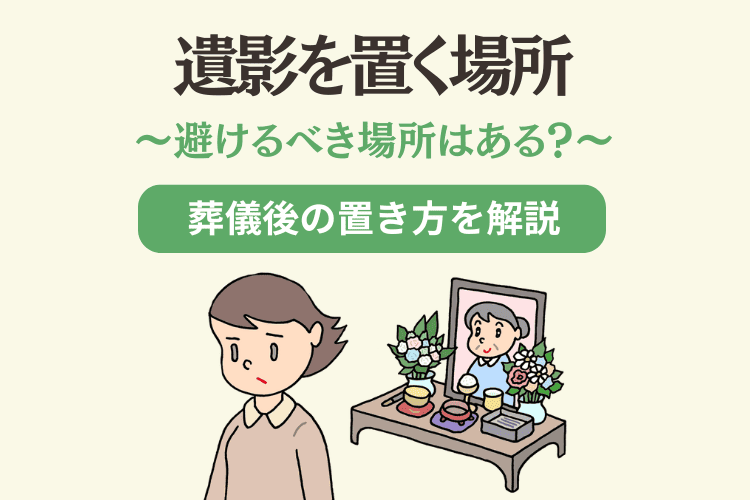
-
遺影の置き場所の正解は?避けるべき場所・注意点・正しい飾り方を解説
2025/11/28
-